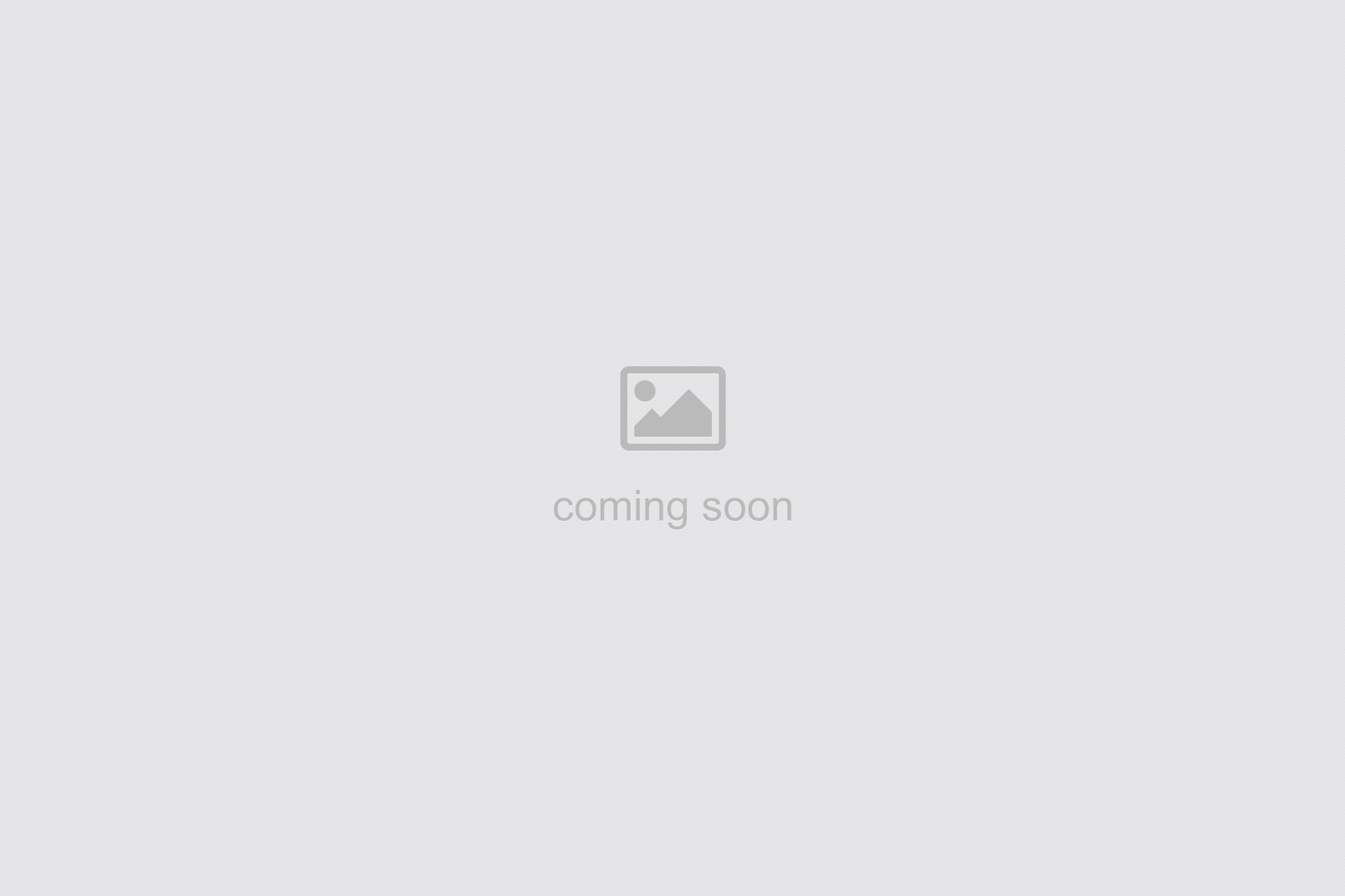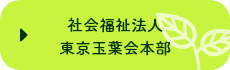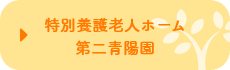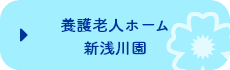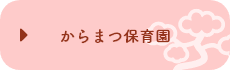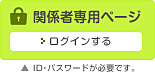介護保険制度のしくみ
介護保険は40歳以上の方が利用できます。
介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な介護サービスを総合的に提供する社会保険制度です。
1.保険者
介護保険の実施主体(保険者)は、八王子市です。
2.加入者(被保険者)
八王子市に住所を有する40歳以上の方が加入します。加入者は2つに分かれます。
加入の手続きは必要ありません。
| (1)第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
| (2)第2号被保険者 | 40〜64歳で、医療保険に加入している方 |
3.サービスを利用できる方
| (1)第1号被保険者 | 寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)の方、 または家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
| (2)第2号被保険者 | 表1の疾病(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態である方 |
表1 特定疾病
| 1.筋萎縮性側索硬化症 2.後縦靱(じん)帯骨化症 3.骨折を伴う骨粗しょう症 4.多系統萎縮症 5.初老期における認知症 6.脊髄(せきずい)小脳変性症 7.脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症 8.早老症 9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎(じん)症および糖尿病性網膜症 10.脳血管疾患 11.パーキンソン病関連疾患 12.閉そく性動脈硬化症 13.関節リウマチ 14.慢性閉そく性肺疾患 15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16.がん末期 |
4.介護保険給付費の負担
保険給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、
公費(税金)と保険料で賄われます。
表2 介護保険給付費の負担 ※居宅サービス費の場合
公費50%(国25%、東京都12.5%、練馬区12.5%) | |
第1号保険料19% | 第2号保険料31% |
※1施設等給付費や地域支援事業(包括的支援・任意事業)については、負担割合が変わります。
※2国負担のうち5%相当分は、区市町村間の高齢者の所得分布や後期高齢者の割合、災害その他特別の事情に応じて調整され、その分第1号保険料の負担割合が上下します。
要支援・要介護認定を受けて、サービスを利用します。
1.申請をします
(1)介護保険の対象となるサービスの利用を希望する方は、認定申請をしてください。
(2)本人や家族が、直接高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や
市役所(市民部事務所含む)等で申請します。
指定居宅介護支援事業者等に代行してもらうことも出来ます。
申請をする場合には、できるだけ「介護保険の被保険者証、主治医の氏名と病院・診療所の名称や
所在地のわかるもの(診察券など)」をお持ちください。
なお、第2号被保険者(65歳未満で特定疾病のある方)の場合、介護保険の被保険者証の代わりに、医療保険の被保険者証が必要です。
2.訪問調査などがあります
(1)訪問調査
調査員が自宅を訪問し、心身の状況や生活の様子を調査します。
調査は、全国共通の基本調査票にもとづく項目と、介護の手間に関する特別な事情(特記事項)等を、
ご本人や家族から聞き取って行います。
(2)主治医の意見書
訪問調査と同時に市から主治医に、身体・精神上の障害の原因である疾病または
負傷の状況等について、意見書の作成を依頼します。
主治医がいない方は、どこかの病院に受診していただく必要があります。
調査員が自宅を訪問し、心身の状況や生活の様子を調査します。
調査は、全国共通の基本調査票にもとづく項目と、介護の手間に関する特別な事情(特記事項)等を、
ご本人や家族から聞き取って行います。
(2)主治医の意見書
訪問調査と同時に市から主治医に、身体・精神上の障害の原因である疾病または
負傷の状況等について、意見書の作成を依頼します。
主治医がいない方は、どこかの病院に受診していただく必要があります。
3.審査・判定があります
(1)審査・判定は、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会が行います。
訪問調査の基本調査票の結果と主治医意見書の一部の項目を入力したコンピュータの一次判定結果、調査員が作成した特記事項および主治医意見書をもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護が
必要かを審査・判定します。
(2)介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護1〜5」および「非該当(自立)」の8段階に分けられます。
訪問調査の基本調査票の結果と主治医意見書の一部の項目を入力したコンピュータの一次判定結果、調査員が作成した特記事項および主治医意見書をもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護が
必要かを審査・判定します。
(2)介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護1〜5」および「非該当(自立)」の8段階に分けられます。
4.認定の結果が届きます
(1)介護認定審査会の二次判定にもとづいて、市が要介護度の認定をし、本人に文書で通知します。
認定の結果は、原則、申請した日から30日で届きます。
(2)決定の内容は、要支援1・2、要介護1〜要介護5、非該当のいずれかです。
要支援・要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できます。(表3)
(3)認定結果に不服がある場合には、介護保険課にご相談ください。
納得できない場合には、通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に
「東京都介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
認定の結果は、原則、申請した日から30日で届きます。
(2)決定の内容は、要支援1・2、要介護1〜要介護5、非該当のいずれかです。
要支援・要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できます。(表3)
(3)認定結果に不服がある場合には、介護保険課にご相談ください。
納得できない場合には、通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に
「東京都介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
5.ケアプランを作成し、サービスを利用します
ケアプランは、どんなサービスを、どのくらい利用するかという計画書です。
ケアプラン作成費用は全額、保険から直接事業者へ給付されます。ご本人の負担はありません。
なお、自分で毎月作成して、市へ届け出ることもできます。
注1 介護サービス利用料については利用したサービス毎に費用が掛かります。
平成27年8月からは収入額に応じて2割・3割負担となる方もいらっしゃいますのでご確認ください
【要支援1・2の方】介護予防サービスを利用するまでの手続き
(1)高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や指定居宅介護支援事業者へ介護保険証を添えて依頼します。
ケアプラン作成について高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)と契約を結びます。
(2)高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師等や居宅介護支援事業者の
ケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を聞き取りして、ケアプラン原案を
まとめます。
(3)原案をもとに担当者が本人・家族、サービス事業者等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを
作成します。
(4)介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
※一定期間後に高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の担当者等が
目標の達成状況を確認します。
注2 平成28年3月から介護予防訪問介護と介護予防通所介護サービスについては
介護予防・日常生活支援総合事業によってサービスが提供されます
【要介護1〜5の方】居宅サービスを利用するまでの手続き
(1)指定居宅介護支援事業者を選びへ介護保険証を添えて依頼します。
ケアプラン作成について契約を結び、担当のケアマネジャーが決まります。
(2)ケアマネジャーが自宅等を訪問して、本人の心身や生活の状況を聞き取りして、ケアプラン原案をまとめます。
(3)原案をもとにケアマネジャーが本人・家族、サービス事業者等と検討を行い、同意を得て、
ケアプランを作成します。
(4)介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
【要介護1〜5の方】施設サービスを利用するまでの手続き
ケアマネジャーの紹介やご本人・家族が直接申し込むことにより、施設と契約を結び入所します。
施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
表3 要介護度ごとの状態の例と利用できるサービス
ケアプラン作成費用は全額、保険から直接事業者へ給付されます。ご本人の負担はありません。
なお、自分で毎月作成して、市へ届け出ることもできます。
注1 介護サービス利用料については利用したサービス毎に費用が掛かります。
平成27年8月からは収入額に応じて2割・3割負担となる方もいらっしゃいますのでご確認ください
【要支援1・2の方】介護予防サービスを利用するまでの手続き
(1)高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や指定居宅介護支援事業者へ介護保険証を添えて依頼します。
ケアプラン作成について高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)と契約を結びます。
(2)高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師等や居宅介護支援事業者の
ケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を聞き取りして、ケアプラン原案を
まとめます。
(3)原案をもとに担当者が本人・家族、サービス事業者等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを
作成します。
(4)介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
※一定期間後に高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)の担当者等が
目標の達成状況を確認します。
注2 平成28年3月から介護予防訪問介護と介護予防通所介護サービスについては
介護予防・日常生活支援総合事業によってサービスが提供されます
【要介護1〜5の方】居宅サービスを利用するまでの手続き
(1)指定居宅介護支援事業者を選びへ介護保険証を添えて依頼します。
ケアプラン作成について契約を結び、担当のケアマネジャーが決まります。
(2)ケアマネジャーが自宅等を訪問して、本人の心身や生活の状況を聞き取りして、ケアプラン原案をまとめます。
(3)原案をもとにケアマネジャーが本人・家族、サービス事業者等と検討を行い、同意を得て、
ケアプランを作成します。
(4)介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
【要介護1〜5の方】施設サービスを利用するまでの手続き
ケアマネジャーの紹介やご本人・家族が直接申し込むことにより、施設と契約を結び入所します。
施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
表3 要介護度ごとの状態の例と利用できるサービス
要介護度 | 心身の状態例 | 利用できるサービス |
要支援1 | 日常生活を送るうえの基本的動作はほぼ自分で行うことが可能だが、家事や買い物などの日常生活を送るうえの能力になんらかの支援が必要な状態。 | 「予防サービス・総合事業」 施設サービス、一部の地域密着型サービスは利用できません。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、わずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態。 | 「予防サービス・総合事業」 施設サービス、一部の地域密着型サービスは利用できません。 |
要介護1 | 要支援の状態から「洗身」や「金銭の管理」など日常生活を送るのに必要な能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 「居宅サービス」 または 「施設サービス」 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、「移動」などの日常生活を送るうえの基本的動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活の基本的動作と日常生活を送るのに必要な能力がとても著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を送ることが困難な状態。 | |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。 | |
非該当 (自立) | 要支援や要介護という状態には至っていない。 | 介護保険でのサービスは利用できませんが、 地域支援事業など市の福祉サービスを利用出来る場合があります。 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)へ ご相談ください。 |
6.暫定サービスの利用
要支援・要介護の認定は、申請日に遡って有効となります。申請時にすぐサービスが必要な場合は、介護保険課にご相談ください。
7.更新の申請
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間が終了する前(60日前から)に、
介護保険更新申請をしてください。
※心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、
いつでも変更の申請ができます。(区分変更申請)
介護保険更新申請をしてください。
※心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、
いつでも変更の申請ができます。(区分変更申請)